CIAJは研究会第10回で
資料10-2(pdf)の3ページにラジオを含む各種機器名を列記し、CIAJ内タスクフォース参加の各企業から問題なしとの回答があったと言及しました。ただし、具体的にどの企業がどのような技術的条件で検討したものか、PLC側、被干渉機器側とも不詳です。
しかし、日経ラジオ社が
資料10-6(pdf)により、「資料9-2の共存条件案(最終的にパブコメに付されたものと基本的に同じ)の許容値・測定法を採用すればPLC導入世帯近傍の50%の世帯で短波放送に有害な混信が生じる」と主張したところ、「住友電工のヒロツ」と名乗る者が発言を求め、短波放送はインターネットラジオに移行しているし、デジタルラジオは市場があるか不明であるので考慮する必要はないとの放言がありました。住友電工は研究会構成員を出していませんが、資料10-2の4ページには「弘津(CIAJPLCタスクフォース)」の記載がありますし、
第6回議事録(pdf)には池田構成員(CIAJ)の同行者としてそれらしき名前が見えますので、CIAJの資格での出席なのでしょう。資料10-2の4ページ4(7)のEC課長の発言の紹介ではなく、明らかに自らの意見としての発言です。
資料10-6は
資料9-4(pdf)で報告された、PLC-Jを共同実験者に含む非専門家24人による主観評価実験の結果に基づいており、資料10-2の3ページに記された「極端に五感が発達している人のケース」として除外することもできないため、技術的な反論は困難とみてこのような反論になったのでしょう。しかし、こんなことを言われて短波放送側は引き下がれるはずもないとみられ、パブリックコメントに付す案を取りまとめる段になってますます推進派と慎重派の溝が深まった感があります。
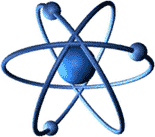
しかし,反論できないから暴言を吐くのでは,ますますPLCに対する風当たりが強くなるだけ。反論できないということは「無線業務に実用上の障害を与えない」ことをPLC-J側が証明できないことを意味する。やけになっているのではないですかね?死なばもろとも,という名目で自殺を図っているに等しい。